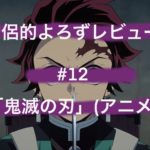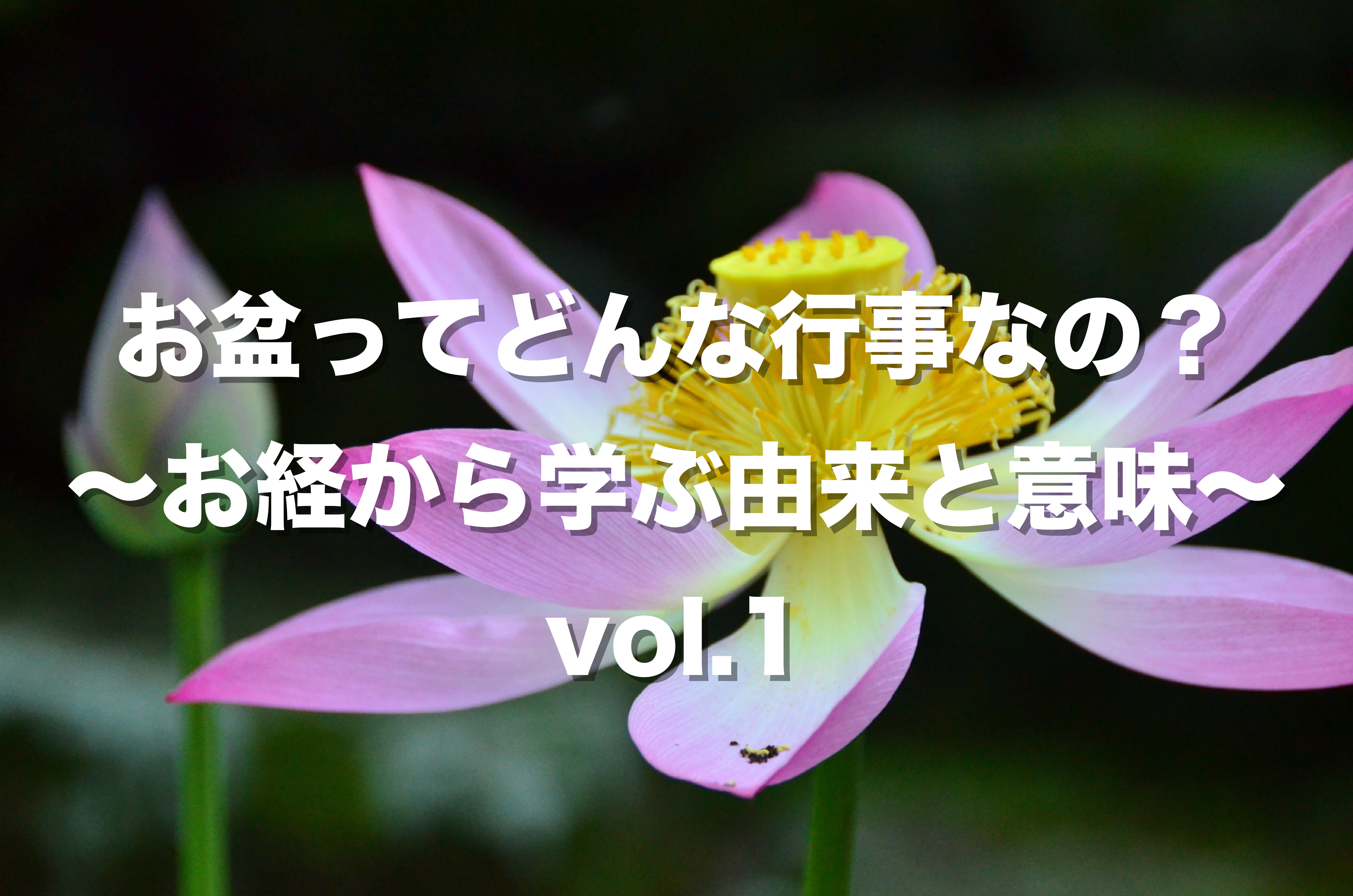
スポンサードリンク
七月十三日、東京などの都市部をはじめ、一部の地域では一ヶ月早い「迎え盆」に入ります。
これは、お盆の由来が説かれたお経に出てくる旧暦の七月十五日のお盆の中日の、日付をそのまま採用したか、今の暦に合わせて八月十五日にしたかで生まれた違いです。
実際のところ、旧暦を今の暦に合わせて八月にしようが、七月という日付を生かそうが、どちらも問題ありません。
元々は七月に農業の忙しくなる地域では新暦で八月、とくに影響のない地域では七月の日付を旧暦のまま生かしたという、実はそれだけのだけの違いなのです。
七月と八月で違いがある理由は、実はこうした日本の風習や気候との関係にあったんですね。
このように、お盆は身近な行事でありながら、意外とその意味や由来は知られていないものです。
そこでこのコラムでは、全4回に分けてお盆という行事の由来や意味を探っていきます。

「仏説盂蘭盆経」をどう受け止めるか?
まずはこのお盆という行事、正式名称は「盂蘭盆会」と言います。
冒頭でも少し触れたように、『仏説盂蘭盆経』というお経の中に日本のお盆の原型となる盂蘭盆会の様子が説かれています。
ただしこのお経、仏教学者やお坊さんの中では評価が分かれるんです。
お経というのは、玄奘三蔵のような訳経僧がインドで書かれたお経を中国語に訳すことで中国に広がっていきました。
そしてその翻訳の元となるインドのお経が見つかっていないお経のことを「偽経」という呼び方をしたのです。
そうした理由から、偽経とされている「仏説盂蘭盆経」の評価は賛否が分かれてしまっているのです。
では、インドに原本がないからといってお経として価値が無いのか、仏教の教えに合っていないのかというと、そんなことはありません。
その土地の信仰や風習の影響を受けすぎて、さすがに仏教的にどうなの?というお経が無いわけではありません。
しかし、全く異なる文化圏でできたお経だからこそ、その土地のその当時の修行僧たちの切実な問題を反映しているものがたくさんあるのです。
私の師匠が師事した、駒澤大学の教授であられた故・太田久紀先生は「お経は読み手の受け取り方次第でいくらでも学びようがある」とおっしゃっていたそうです。
このコラムでは、「仏説盂蘭盆経」に込められた盂蘭盆会という行事の意味に迫ります。
私たちは「仏説盂蘭盆経」をどのように受け止め、盂蘭盆会をどのような行事として捉えるべきなのでしょうか?