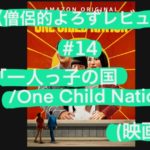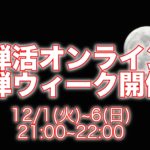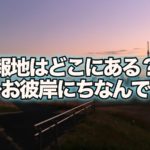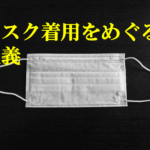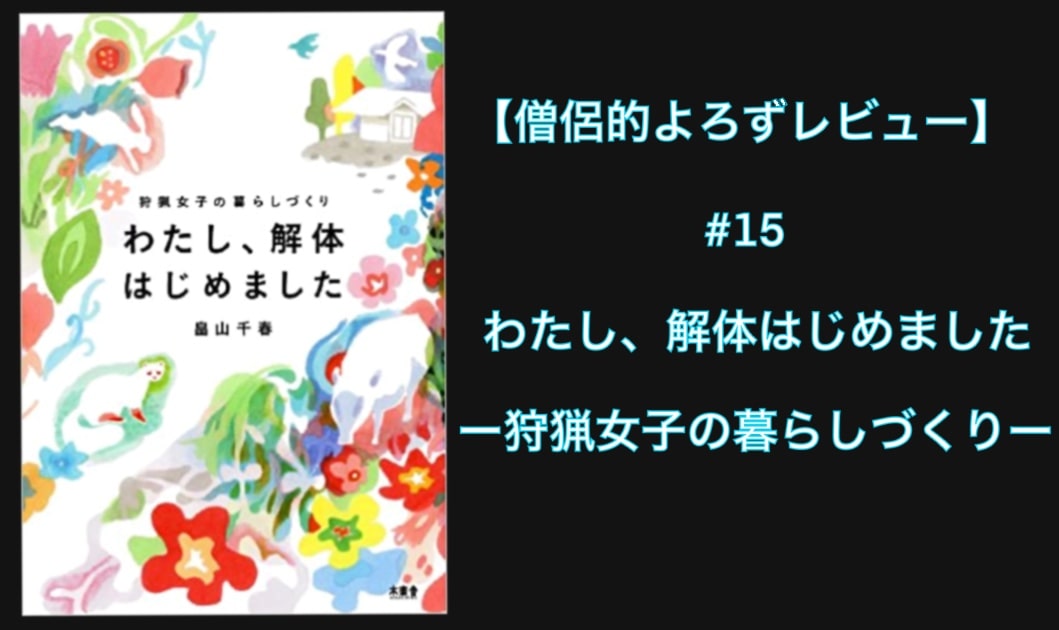
スポンサードリンク
僧侶の視点から様々なものをレビューする【僧侶的よろずレビュー】。
前回は映画「一人っ子の国/One Child Nation(原題)」をレビューしました。
#15となる今回は、都会暮らしをしていたごく普通の女性が、田舎に移住して狩猟生活を送るようになった体験記「わたし、解体はじめました ─狩猟女子の暮らしづくり─」という本をご紹介します。
Contents
#14「わたし、解体はじめました ─狩猟女子の暮らしづくり─」
内容
この本は、狩猟女子としてそのブログが話題になった畠山千春さんが、ご自身の狩猟生活の体験を綴ったノンフィクション作品です。
1986年生まれの畠山さんは、都内の大学を卒業して映画配給会社に就職、神奈川県でごく普通の社会人生活を送っていたそうです。
そんな生活が大きく変化したのが2011年3月11日、東日本大震災でした。
直接的な被害に遭うことはなかったものの、スーパーから食糧が消え、自分では何も食べ物を手に入れられないという現実に、畠山さんは衝撃を受けます。
それを機に食糧事情について考えるようになった畠山さんは、ついてに福岡県の山間部の古民家へ移住、自給自足の生活を始めるのです。
自給自足の中でも、畠山さんが力を入れたのが「肉」。
自ら鶏を育てたり、免許を取得して猟にもでます。
命をもらって生きているということを、肌で感じ取り、生きていくということを考えていく作品です。

畠山さんのブログ(現在休止中)より引用
畠山さんの行動力と感受性
現在、私は「肉を食べるということ」という連載も書いているように、肉食の捉え方を僧侶としての大きな課題としています。
肉は現代のご馳走の代名詞の一つであり、メディアにとっては目玉コンテンツとなり、市場にも大きな影響を与える食品といえます。
しかし、その生産の過程はタブー視され、解体に携わる方々が不当な差別や偏見にさらされてきたという歴史があること、それが現代でも無くなってはいないということは、過去に記事で触れた通りです。
私はその事実を知り、実際に食肉加工場で現場の声を聞いた時に大きな衝撃を受けました。
そして、仏教の立場ではどう捉えるのかを考えるようになりました。
一方で、著者の畠山さんは自分自身で獲るという選択をします。
その行動力一つをとってもなかなか真似できるものではありません。
ところがさらに驚くのは畠山さんの感受性の高さです。
本文には、僧侶が思わずハッとさせられる、食の本質、命の本質に迫る言葉が多々あります。
自分で育てた鶏を捌いて食べる時、罠にかかった猪に止めを刺して解体して食べる時、自分がその場に居合わせたら動揺してしまうような場面がいくつもあります。
もちろん、畠山さんも動揺しないわけではないのですが、解体の場で紡がれる言葉や抱く思いは、罪悪感や後ろめたさではなく、命に対する感謝やそれを食べて生きるということへ強い責任感なのです。
これは実際に体験をした人にしかわからないことなのかもしれません。
食肉加工場の見学をしたとはいえ、私は自分で解体をしたわけではありません。
自分の手によって今まさに動物が食物へと変わる瞬間、それを感じている畠山さんの言葉と、そうした命の移り変わりを感じとる豊かな感性は、読者を惹きつけます。

「残酷」とは何か
畠山さんは生きるために食べるという、生物の根本的な営みを行っているとはいえ、狩猟や解体が非難やバッシングにさらされることもあるようです。
以前、畠山さんはご自身のブログで、猟師さんが仕留めた兎を食べ、毛皮をなめした様子を掲載したところ、たくさんの「残酷」という意見で炎上してしまったそうです。
しかし、肉を食べ、毛皮を活用するということは古くから行われてきたことで、動物の命を余すことなくいただく知恵でもあります。
食肉加工場でも、肉、内臓、脂、皮と余すところなく全て有効に使えるよう、作業には細心の注意を払います。
こうした現場の皆様の姿勢は、曹洞宗の不殺生の捉え方に通ずるものさえあります。
ところがこの「残酷」という感覚が、世界中で食に関する争いを生んでいます。
日本の捕鯨、中国や韓国での犬肉食など、世界には異文化圏から見た「残酷」によって一方的に非難される食文化や営みがあります。
ではこの「残酷」という感覚はどこからくるのでしょうか。
それはやはり、「自分の中の常識」や価値観なのだと思います。
「これは食べる物」「これは愛でるもの」「これは避けるもの」という、自分という人間を中心に構築した世界観に反するものに出会った時、人から「残酷」や「グロテスク」「ゲテモノ」という言葉が生まれるのです。

命の循環の中にいることの気づく本
そうした「残酷」という感覚は、食物を生産する過程に直接手を下すことが少なくなった人間の、一つの勘違いなのではないでしょうか。
畠山さんは、自分が大怪我をすることになるかもしれない、下手をすれば食べられる側になるかもしれない環境の中で感じたことを、この本では語ってくれています。
いわば食物連鎖の中に身を置きながら声を届けてくれているのです。
私たち現代人は、動植物を食べることはあっても、自分がその身を差し出すことはありません。
「食べられてしまうかもしれない」なんていう感覚は、長らく味わわないうちに、いつの間にかDNAが忘れてしまったようです。
そしていつの間にか、「生きている動植物の命をいただいている」という感覚が弱まり、こじれてしまっているように思います。
お金によって食物を手に入れる私たちは、食べる命と食べない命を、無意識に選別してしまっているのではないでしょうか。
本来食というのは、単なる栄養の摂取ではなく、その命、その土地、その世界とのご縁いただき「生きる」ということそのものでした。
畠山さんは、直接動物の血の温もりに触れ、野菜や蜂蜜も自分で作りながら、食物に対しては全て平等な感謝の心を示します。
それは、都会で自分が失いかけていた「食べ物という命と縁で繋がるという感覚」を、自らの行動によって取り戻したからこその感覚なのかもしれません。
しかし、それは現代の私たち誰もが今一度呼び起こさなければならない感覚なのだと、私は思います。
この一冊を通して、動物を解体するという体験はできなくとも、その心境を追体験してみてはいかがでしょうか?
まとめ
今回は、現在「肉を食べるということ」で取り上げている不殺生とも大きく関係するこちらの一冊をご紹介しました。
私がお伝えしたかったのは、「肉を自分で手に入れていないことが悪い」ということではなく、誰もがこうした営みと間接的につながっているということです。
食べるということはご縁をいただいて生きるということ。
この本は、そんな生きるということの根本的な部分を、私たちに思い出させてくれます。
オススメです。
こんな人にオススメ
・肉食に関心のある方
・里山での暮らしや狩猟に興味がある方
・複雑な文章よりもシンプルな口調が好きな方