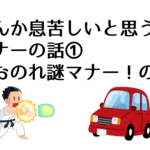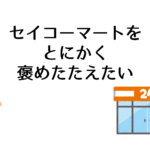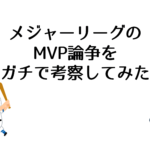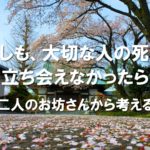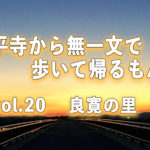スポンサードリンク
今回は、野生動物への餌付けについて考えてみたいと思います。
Contents
境内から飛び出てきたキタキツネ
つい先日の話です。
地元北海道のお寺に帰省し、空いた時間で畑仕事をしていた時のこと。
作物への水やりを終えて、ほっと一息ついていると、お寺の境内から一匹のキタキツネが飛び出してきました。
北海道のキタキツネ。
愛らしい見た目のため(特に生まれて間もないキツネは本当にかわいい)人気の高い動物ですが、地元に住む人間にとってはかなり厄介な存在です。
納屋や物置に巣を作ったり、そこら中に糞をしたり、畑に侵入して農作物を荒らしてしまうなど……
害獣に他なりません。
なんとも迷惑なキツネですが、もっとも恐ろしいのはキツネが宿している可能性のある
寄生虫「エキノコックス」です。
人体に寄生すれば、数年から数十年の潜伏を経て、時に人を死に至らしめることもあるヤバいやつ!
北海道の山間部に暮らす人は、子どもの頃から野生動物に触れるリスクを徹底的に教え込まれます。
そんなわけで、お寺の敷地から飛び出してきたキツネを見て、
「居付かれたら困るなあ」
と思っていたのですが、
さらに驚くことに!
そのキツネは手のひらサイズの丸いパンを口にくわえていました。
「餌付けしている人がいるのかい!」
もしかすると、どこかから盗んできたのものなのかもしれませんが、
話を聞いたところ、やはり餌付けをしている人がいるようです。
餌付けの問題点
言うまでもなく、野生動物への餌付けはマナーとして最低の行為です。
北海道環境局自然生活課のHPでは「安易な餌付け」についてこのように警告しています。
農作物等への被害や人身被害等をもたらす鳥獣を誘因することになり、被害を増加させるばかりでなく、被害防止を目的に捕獲される鳥獣を増やしてしまうおそれがあります
また、
野生鳥獣への安易な餌付けは、次の理由などで生態系に影響を与えるおそれがあります。
1 人が与える食物に依存して自ら餌をとることができなくなる鳥獣を生じさせます。
2 人の食べものは、野生鳥獣が本来食べることのない、様々な調味料や添加物、油分等が含まれており、病気等にかかる鳥獣を生じさせることも心配されます。
3 餌付けされた種のみが増加することにより、生態系のバランスを乱すことも予想されます。
4 餌付けに依存することにより、渡りや移動のルートや時期にも変化を及ぼすことが心配されます。
とあります。
さらに同ホームページでは、鳥類への餌付けが、特にリスクの高いことなども説明されておりました。

実際に私の地元では、街中にキツネが増えすぎたため、野良猫がほとんど見られなくなったそうです。(キツネは子猫を喰らう)
無責任な餌付けは、当事者が想像している以上に自然環境に大きな影響を与えるのです。
行為の責任と影響力
確かに野生動物の愛くるしさは、私たちの心を奪います。
キタキツネ(かわいい)、

ヒグマ(こわいけど見てる分にはかわいい)、

オコジョ(すごくかわいい)、

シマエナガ(キュンキュンする)、

過酷な自然環境の中で力強く生きる動物たち。
ふいにこうした動物に出くわし……しかもそれが人懐っこく近づいてきた。
そうなったとき、その動物に何かを与えてあげたい、助けになってやりたい、と思うのも確かに自然な感情なのだと思います。
思わず持っていた食べ物を与えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、私たちの行為には、必ず結果と責任が伴います。
近年、飼い切れなくなり捨てられたペットが外来種として定着し、在来種を脅かすという事態が問題視されておりますが、
一つの行為がもたらす影響力というものは、往々にして自分が想定しているそれより大きく広がっていくものです。
自分の行為が、果たして本当に相手のためになるのか、どのような結果を導くのかを、しっかり考える必要があります。
自然との共生を考える
人間は自然の恩恵を受けながら生きています。
近年、いかにして自然と共生していくか、というテーマが重要視されておりますが、文明社会に生きる現代人が全く手つかずの自然環境の中で生きていくことはほとんど不可能であると言えるでしょう。
自然に寄り添いながら生きるためには、自然と人間世界の間に境界線を張り、お互いに適切な距離を保ちながら付き合っていく必要があります。
本当に野生動物が愛らしいのであれば餌付けをするよりも、
大きな声を出して追い払ったり、
ぼっこ(北海道弁で「棒」の意)をもって追い掛け回したり、
多少手荒でも、人間の領域がその動物のいるべき場所でないと気付かせることこそが本当に必要なのではないでしょうか。
最後に……
防獣ネットを潜り抜けて畑に糞をしていくのをやめてくれませんか、キツネさん(泣)
続きます↓