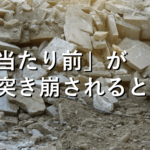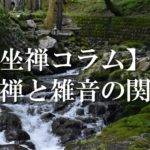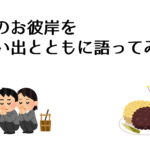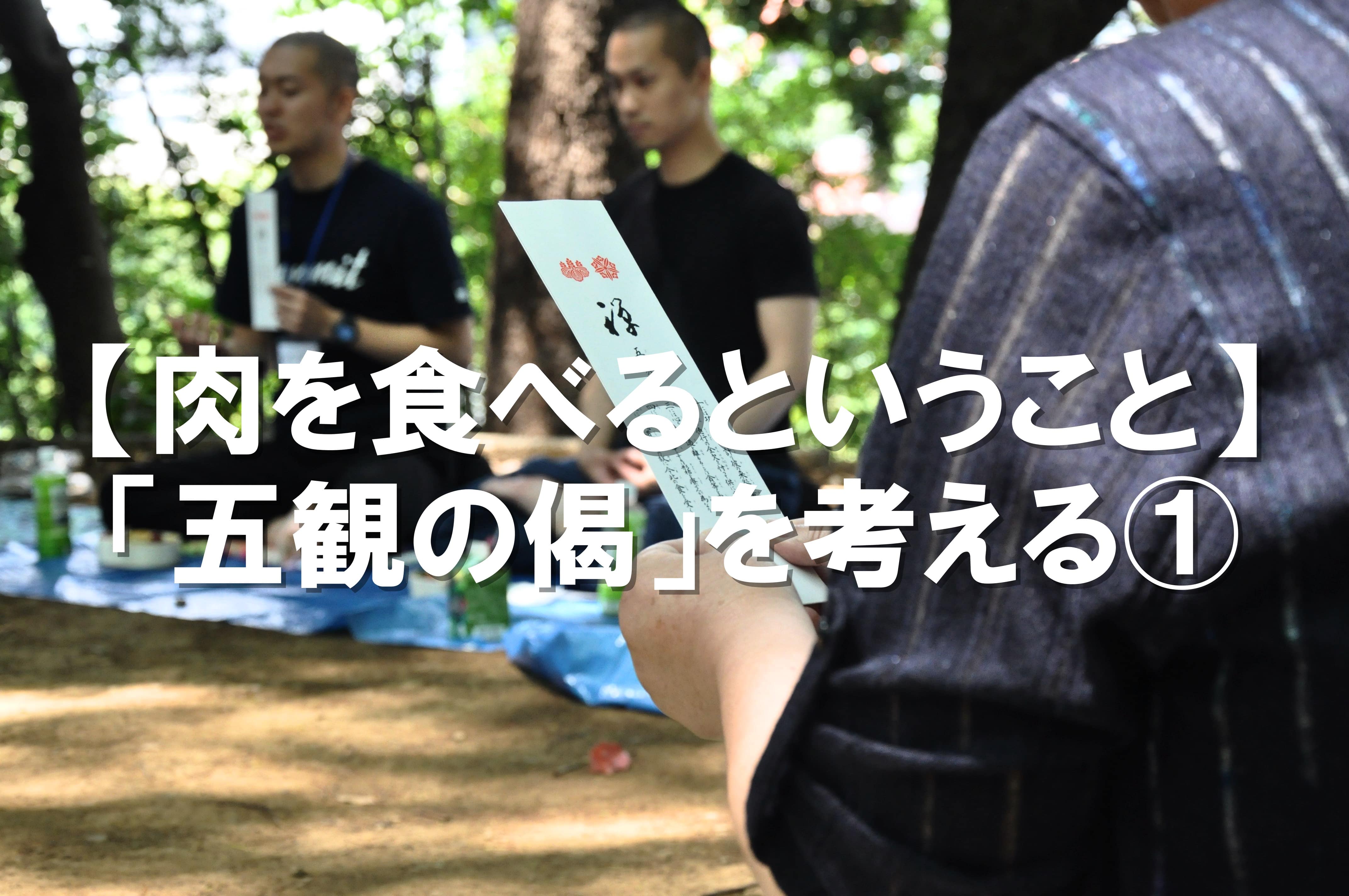
スポンサードリンク
曹洞宗僧侶の立場から肉食を考えてきたこちらの連載。
前シリーズでは、曹洞宗の立場から見た食べ物の「いのち」、そして不殺生との解釈と実践についてお話ししました。
そして今回からは、曹洞宗の食に関する布教の現場でよく用いられ、修行道場でもお唱えをする「五観の偈」から、肉食はもちろん、「食べる」ということそのものを、見渡していきたいと思います。
Contents
「五観の偈」とは
「五観の偈」は、曹洞宗の食の教えに触れた方ならかなりの高確率で触れているであろう、最もポピュラーな食前のお唱えごとの一つです。
「五観」というのは、字の通り五つの視点から観ることで、「偈」というのは偈文、要は短い詩句のことです。
つまり、「五つの視点から観る短い詩句」ということですね。
その全文は以下の通り。
一計功多少量彼来処(一つには功の多少を計り、彼の来処を量る)。
二忖己徳行全欠応供(二つには己が徳行の、全欠を忖って供に応ず)。
三防心離過貪等為宗(三つには心を防ぎ過を離るることは、貪等を宗とす)。
四正事良薬為療形枯(四つには正に良薬を事とするは、形枯を療ぜんが為なり)。
五為成道故今受此食(五つには成道の為の故に、今此の食を受く)
『四分律行事鈔』と「五観の偈」
この文章は中国の僧、南山道宣が記した『四分律行事鈔』という書物(正式には『四分律刪繁補闕行事抄』)に登場します。
この書物は、お釈迦様が説かれた生活規範である『四分律』を、およそ1000年後の中国で、改めて捉え直したものです。
まずはこの『四分律行事鈔』と『四分律』の違いについて、簡単に触れておきましょう。
元々、民間から托鉢によって食事を得る修行生活をしていたお釈迦様は、『四分律』の中では肉食そのものを禁止することはありませんでした。
ただ、人・象・蛇・犬など、食べることで何らかの不具合が起こる特定の肉と、自分のために食肉にされるのを「見た・聞いた・その疑いがある」肉を口にすることを禁じました。
この辺りは過去の記事で触れています。
ところが、中国で南山道宣によって書かれた『四分律行事鈔』は、全面的な肉食の禁止を説きます。
実はここには、お釈迦様が亡くなって以降のインドの宗教界の流れが関係しています。
お釈迦様が亡くなって以降、インドでは仏教が衰退し、一方でジャイナ教やヒンドゥー教といった肉食を避ける宗教が力をつけ、「宗教者=菜食」という見方が強まっていったそうです。
そうした社会の潮流を受けて、仏教は徐々に肉食を避けるようになり、その頃にできた経典は肉食を禁じるものとなりました。
そして、この頃の経典を参考にして書かれたのが『四分律行事鈔』だったのです。
その中で説かれる「五観の偈」なので、元々は菜食を想定して説かれていることは間違いありません。
そこで、曹洞宗の教えと現代社会の状況を踏まえて、改めて解釈をしていくのが、禅活として活動する私の役目、ということです。

意外と知られていないこと
五観の偈は、今では「お唱え」をするものとして定着していますが、曹洞宗の食作法が説かれる『赴粥飯法』では、唱えるのではなく頭の中で自らを振り返る「観法」として示されています。
つまり、口に出さず頭の中で振り返るものなのです。
私たち僧侶は、修行に行くにあたって、意味はさておき、まずは覚えて唱えるところから入ってしまいがちですが、その意味を理解しておくことが本来必要なんですね。
ということで、次回以降は「五観の偈」を、ここまで触れてきた曹洞宗の食の教えの立場から捉え直し、材料や国に限定されない「食」そのものの理解と、食から考える生き方についてお話ししていきたいと思います。
今後の社会で、異なる食文化や信条を分かち合っていくための一助になるようなものになれば幸いです。
それでは、次回もぜひお付き合いください。