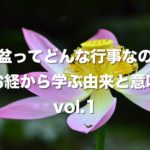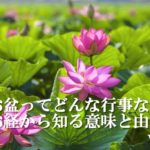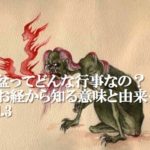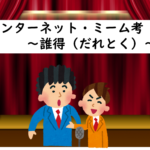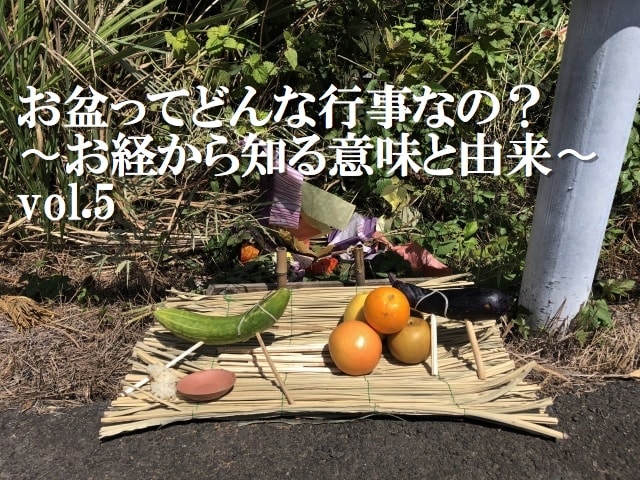
スポンサードリンク
日本人に馴染み深い仏教行事であるお盆の意味と由来をお経から学ぶこちらのコラム。
ここまで4回に渡って、お盆という行事の由来である「仏説盂蘭盆経」の登場人物 ・社会背景・ストーリーを追ってきました。
最終回となる今回は、現代に生きる日本人はお盆をどう受け止めていくべきなのかを考えます。
次の項目では、各回の要点をまとめていますので、今回の内容に飛びたい方は「本当に供えるべきもの」からご覧ください。

Contents
これまでの要点
各回の要点をまとめると以下のようになります。
①お経の概要と時代背景
中国で成立したとされることから「偽経」に分類される「仏説盂蘭盆経」。
そのため、お経として軽視されてることがありますが、その背景には当時の中国の修行僧の悩みが隠れているのでは?
②登場人物とお経の「裏テーマ」
主人公は長男でありながら出家をした目連尊者。
当時の中国では、長男は老後の親を養い、子孫を残すことが最重要とされていました。
にも関わらず出家をした中国の僧侶は、目連尊者に自分の姿を重ねたのでは?
③餓鬼という描写と僧侶の心
お経のストーリーは、餓鬼道に堕ちてしまった母を目連尊者がなんとか供養して救いたい、というもの。
ここで重要なのは餓鬼の「供養が届かない存在」という特性でした。
自分は出家してしまい息子として供養してやれなかったという負い目や不安、これが餓鬼道に堕ちた母の正体なのでは?
④母を救う方法
お釈迦様が示した、母を餓鬼道から救う方法は「7月15日に修行僧に供養をする」というものでした。
7月15日の修行僧とは三ヶ月の集中修行期間で仏の心と行いを兼ね備えた三宝そのものとなっています。
7月15日に修行僧に供養をするというのは三宝に帰依をすることであり、三宝への帰依によって母は餓鬼道の苦しみから救われました。
さらにお釈迦様は、今回に限らず、こうして供養をすることで、7代遡った先祖まで安泰である、と仰るのでした。

本当に供えるべきもの
「仏説盂蘭盆経」の一番のテーマは「親や先祖への供養ができていないのでは」という不安や負い目だったと、私は受け止めています。
出家という道を選んだが故に、世間と同じ供養ができないことへの負い目や不安は、私たちも共感できる部分があります。
仕事があってお墓参りに行けない、法事に出られない、中には死に目に逢えなかったという方もいるでしょう。
世の中の風習として、あるいは仏教の儀礼としての供養や孝行ができないことは、その人の心に後悔や負い目を生みます。
しかし、亡き親や先祖への供養というのは、そうした形にとらわれたものではないというのが「仏説盂蘭盆経」の説くところなのです。
お盆の飾りや季節の食べ物など、仏壇にお供えして手を合わせる。
これは亡き人を仏様として向き合う、お盆のとても大切な時間です。
ただし、それができないからといって供養ができないわけではありません。
むしろ、本当に供えるべきものは、どこにいようと供えることができるのです。
7月15日に修行僧へ供養をするのは、仏教の信仰である三宝への帰依であることは前回お話しした通りです。
そしてその三宝への帰依というのは、入信とか信仰とか仰々しいことではなく、一つの生き方のことです。
その生き方とは自己中心的にならず、奪うより与えることで訪れる穏やかな心で生きるという、仏教の説く生き方です。
三宝への帰依は、仏教の説く生き方へつながり、仏教の説く生き方をすることはすなわち三宝への帰依になります。
そしてこの生き方こそが、亡き親や先祖に供えるべき一番のお供え物だったのです。

これからのお盆を考える
忙しさの中で「生き方」を供える
忙しい社会生活を送る中で、誰しも一度は、亡くなった親や先祖の恩に報いることができているだろうか、向こうでどんな顔しているだろうかという不安を抱いたことがあるはずです。
しかしそれは法事やお墓参りなど、目に見える仏教の儀礼を頭に思い描いてしまうからではないでしょうか。
お仕事の忙しい方や外出が大変な方にとっては、お墓参りや法事への参列も容易ではない場合もあるでしょう。
しかし、なによりも大切なのは私たちが今「どんな生き方をしているか」ということ。
たとえ忙しくてお墓参りに行けなくても、その生き方が正しいものであれば、立派な先祖供養になっていくのです。
自分を振り返る機会としての「お盆」
もちろん、今に伝わっている日本のお盆の風習には、亡き親や先祖への細やかな心遣いが詰まっていて、それ自体が仏教の生き方の実践につながる大切なものです。
ただ、せっかく盂蘭盆会という行事を行うからには、7月盆でも8月盆でも、今の自分へと生命をつないでくれた先祖を思い、今の自分の生き方を確認する機会にしてみてはいかがでしょう。
そうすれば、たとえ忙しくてお墓参りに行けなくても、「私の生き方を見ていてください」という思いで堂々としていればいいのです。
そして少し余裕ができた時に感謝の意味を込めてお墓参りにする。
それでいいのではないかと、私は思います。
供養とは、僧侶がお経を読むことではありません。
一人一人が亡き人に「生き方」を供えるつもりで生きていくことです。
私がこのコラムを通してお伝えしたかったことは、お盆と言えど仕事を休めない方々や、遠方でお墓まで足を伸ばせない方々も、今そこでの生き方が亡き人への供養になるということです。
そしてこのコラムが、お盆という行事を私たちの人生にとって意味あるものとして再確認するきっかけになれば、幸いです。

「お盆ってどんな行事なの?〜お経から知る意味と由来〜」おわり