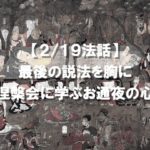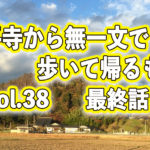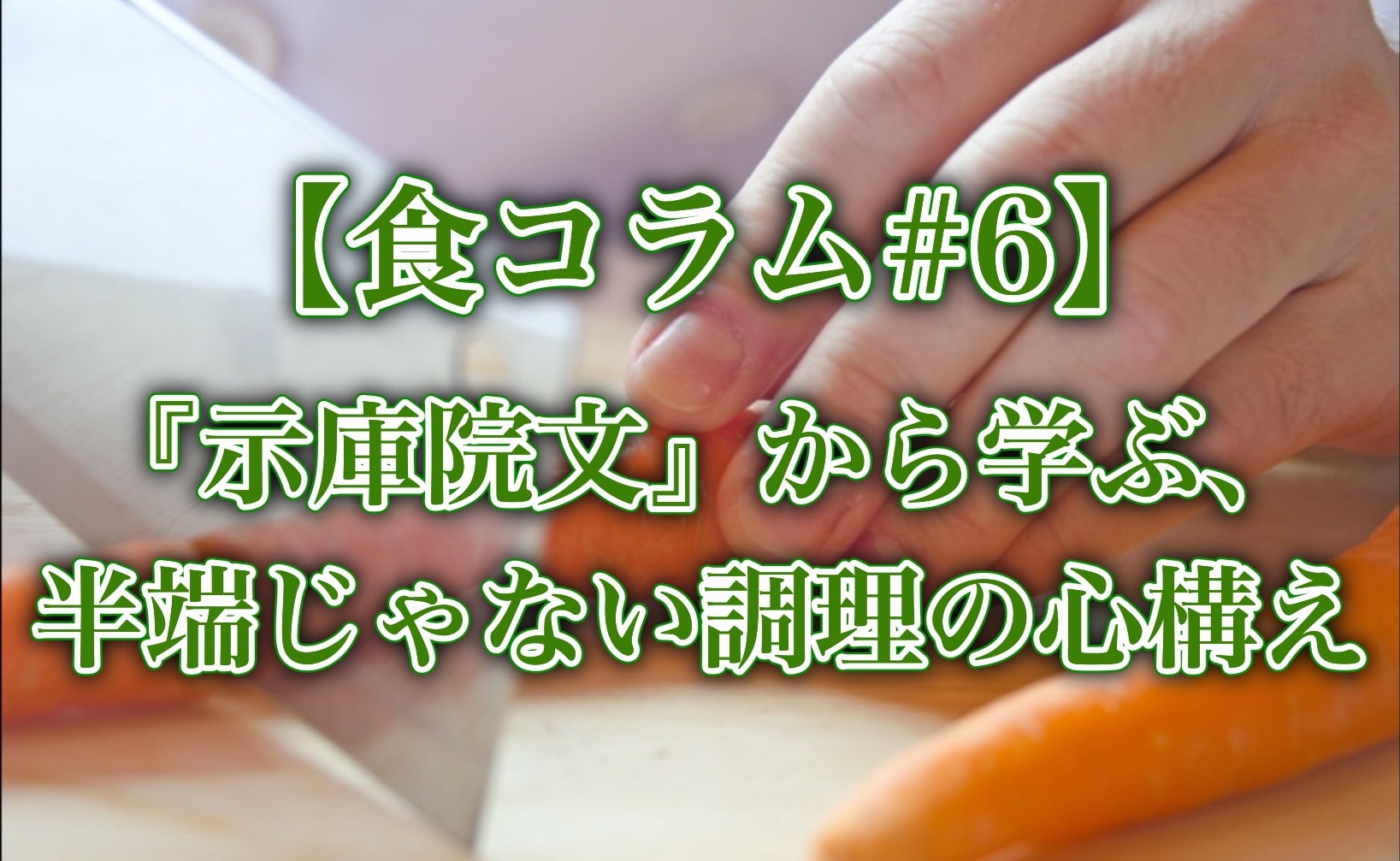
スポンサードリンク
食に関するあれこれを考える食コラム。
前回は「精進料理」という名称について考えてみました。
曹洞宗の食に関連して色々と調べていると、
「永平寺を開かれた道元禅師は精進料理の基礎を作った」
という文言を見かけることがあります。
精進料理という名称や食文化は曹洞宗から生まれたものではないとして、その精神性に道元禅師が及ぼした影響は小さくないでしょう。
それまでは僧侶が調理をするということが当たり前ではなかった日本で、中国で学んだ「典座」という修行の在り方を伝えたことは、仏教界にとっても大きなご功績であったと考えられます。
そんな、道元禅師が調理の精神性を示された書物というと、有名なのは『典座教訓』でしょう。
私も、これを調理の心構えを説いた書物として大変参考にさせていただいてきたのですが、さらに具体的な書物がありました。
それが同じく道元禅師が示された『示庫院文』です。
庫院とは修行道場で調理場がある建物のことで、ここでは庫院での心構えが説かれるのですが、これが私の想像を遥かに超えるものだったんです。
今回はそんな『示庫院文』に説かれる、半端じゃない心構えをご紹介します。
Contents
①食べ物には最敬礼
まずはこちらの文をご覧ください。
いはゆる粥をば、御粥とまをすべし、朝粥ともまをすべし、粥とまをすべからず。
(中略)不敬はかへりて殃過をまねく。功徳をうることなきなり。訳)粥といわれるものを呼ぶ場合には、御粥と申し上げなさい。あるいは朝粥と申し上げなさい、粥と呼び捨てにしてはいけません。
(中略)うやまいの気持ちがなければ逆にわざわいを招くことになる。せっかく修行僧に供養する食事を作るというすばらしい仕事をしていながら、うやまいの気持ちがなければ功徳も得られないのである。『作る心食べる心』「示庫院文」中村璋八・石山力山・中村信幸(第一出版・1985年)
要するに食べ物を呼び捨てにしてはいけない、敬いなさいということが説かれているのですが、こんな書物が他にあるでしょうか。
他にも、米を洗い研ぐことは「お米を洗って浄らかにし申し上げる」と言うようにも説かれます。
なぜそこまで…と思いますよね。
これには二つの意味が想像されます。
一つは、食物を手に入れる、ましてやお米を手に入れるということが決して当たり前でなかった当時、その存在は現代の私達に計り知れない貴重なものだったということ。
二つめは、それが修行僧が食べるものであるということです。
お盆の記事でも触れた通り、曹洞宗の信仰では僧侶、ひいては仏教の実践者はお釈迦様のさとりと道を身の上に体現した存在です。
つまり典座として修行僧に食事を用意することは、仏教の三宝に食事を供養することになります。
現代でもお客さんに出す食べ物を「飯」とか「米」と言わないように、仏様の食事となる食材に対して敬意を表していたわけですね。
解説
現代日本では、食べ物は栄養という役割の止まらず、写真や映像、時には娯楽として消費されるものともなっています。
それは、食べ物があるということが当たり前になってしまった社会では無理もない現象なのかもしれません。
それでも、食を軽んずることは命を軽んずることです。
ここで説かれるほどかしこまらなくてもいいかもしれませんが、「飯」「米」「食う」ではなく「ご飯」「お米」「いただく」くらいの言葉遣いはしていきたいものですね。

②油断禁物
続いては、調理中の注意点となる文。
身のかゆきところかきては、かならずその手あらふべし。
齋粥ととのへまゐらするところにては、佛経の文および祖師の語を諷誦すべし。訳)身体の痒いところを掻いたなら、必ずその手を洗いなさい。
昼食や朝食を用意し申し上げる場所では、仏教の経典や古えの勝れた指導者達の言葉をとなえなさい。『作る心食べる心』「示庫院文」中村璋八・石山力山・中村信幸(第一出版・1985年)192頁
前半部分は、その前に頭や顔を触ったら手を洗う、食べ物に着物が触れないようにする、という内容から続くのですが、鎌倉時代に書かれたとは思えない現代でも通用する衛生意識の高さです。
道元禅師という方は、お手洗いの作法や歯磨きの作法も綿密に説かれた方ですが、調理においてもその綿密さが発揮されているわけです。
もちろん、この食事は修行僧が食べるから、という信仰心も含んだ教えではありますが、私達の日常生活、特にこうした時代には疎かにしてはいけない部分ですよね。
そして後半部分は、修行僧たちに供養する食事を用意する場において、無駄口を叩いてはいけない、ということですね。
これには私も驚きました。
口に出すなら経典や祖師の言葉を唱えなさいとおっしゃるわけです。
仏道修行として調理をしているのであって、雑務をこなしているわけではないのだ、という一瞬の油断も許さない、志の高さを感じずにはいられません。
解説
文明の発展と共に、食事は栄養の摂取だけではなく、娯楽や商売として様々の要素を含むようになりました。
実際に私もYoutubeで調理の様子を配信したりしていますが、果たしてこうした意識をどれだけもっていたか…。
僧侶として調理をするからには、単なる娯楽ではなく、喋るにしてもしっかりと仏道の上で言葉を発さなければ、と自らを戒めました。

③道具は正しく使う
そして最後に、道具に関してこんなお示しがあります。
齋粥をととのへまゐらする調度、ねんごろに護惜すべし、他事にもちゐるべからず
訳)昼食や朝食を用意申し上げるいろいろな道具類は、心を込めて大切に保管しなさい。
ほかの事に用いてはいけません。『作る心食べる心』「示庫院文」中村璋八・石山力山・中村信幸(第一出版・1985年)194頁
これは文章としてはあまり難しくないので、ポイントに移りましょう。
解説
今は本当に調理器具などは値段がピンからキリまであり、100円ショップでほとんど揃えることもできてしまいます。
しかし、そうして手軽に手に入れた道具の危ないところは、捨てるのも手軽になってしまうという点です。
安いやつだから、と無理な使い方をして壊してしまい、「あ〜壊れちゃった」と捨てるのは、【肉を食べるということ】で触れた不殺生の視点から考えてもよろしくないですね。
またここでいう「他のことに使ってはいけない」というのは、調理に使っている道具のことで、キッチン用品は他の用途で使ってはいけない、ということではありません。
つまり、調理用に買って使っていた包丁を、極端な話でいえば急に現れた害虫退治に使ってしまうとか、お鍋をお風呂で使うようなことがあってはいけない、ということですね。
物を正しい使い道で大切に使う。
これは実は簡単なようで難しいことなのかもしれません。
使い道と使い方。
調理道具に限らず、生活全てにおいて言えることですね。
スマートフォンやPCを人を傷つけるために使ってはいけない、というところにも通じているような気がします。

まとめ
いかがでしたか?
『示庫院文』は『典座教訓』と比べると僧侶の間でもややマイナーな書物ですが、当たり前のようで非常に大切な、現場に根ざした教えが詰まっています。
それは「厳しさ」というものではなく、調理を生き方とリンクさせていく教えともいえるでしょう。
テクニックやルールではない、指針として、調理の心構えを大切にしていきたいですね!